「海外のどの国を狙えばいいのだろう?」
「自分の商品が海外で売れるのか不安…」
そんな悩みを抱える事業者の方は少なくありません。
しかし、適切な戦略と市場理解があれば、越境ECは大きなビジネスチャンスとなります。
この記事では、実際の成功事例をもとに、越境ECで売れやすい商品ジャンルと、最新の市場トレンドを見極めるポイントを解説します。
この記事を読み終えれば、あなたも自社の強みを活かした越境EC展開の道筋が見えてくるでしょう。
拡大する越境EC市場の現状
越境EC市場は年々拡大しており、日本企業にとって大きなビジネスチャンスとなっています。
コロナ禍以降、世界中の消費者のオンラインショッピング習慣が定着しました。
経済産業省の調査によると、日本企業の越境EC市場規模は年々増加傾向にあり、特にアジア圏では日本製品への信頼度が高く、人気を集めています。
日本製品は「安心・安全・高品質」というイメージが定着しており、この強みを活かせばさらなる可能性が広がるでしょう。
越境ECで売れる日本製品の人気カテゴリー
日本製品は海外で高い評価を受けていますが、特に売れやすい商品ジャンルがあります。
ここでは、実際の成功事例から見えてきた人気カテゴリーを紹介します。
アジアで人気!化粧品・スキンケア製品の成功ポイント
日本の化粧品・スキンケア製品は特にアジア市場で高い人気を誇ります。
中国や台湾、タイなどでは「日本製」というだけで品質の高さが認められています。
成功のポイントは「日本製」という信頼性に加え、現地のニーズに合わせた商品選定です。例えば、東南アジアでは紫外線対策商品が年間を通じて需要があります。
パッケージデザインも重要で、日本らしい繊細なデザインや和風要素を取り入れた商品は注目されやすいでしょう。
日本のアパレル・雑貨の越境EC売れ筋トレンド
日本のファッションやアパレル商品は、独自のデザイン性と高品質が評価されています。
特にシンプルで機能的な日本のカジュアルブランドや、ユニークなデザインの雑貨類が人気です。
欧米市場では「ジャパニーズミニマリズム」として日本のシンプルなデザインが注目されています。
日本らしい「かわいい」「シンプル」「機能的」といった要素が入った商品が好まれる傾向にあります。
健康志向で注目される日本食品の越境EC戦略
健康志向の高まりとともに、日本食品への関心も世界的に高まっています。特に抹茶や緑茶、発酵食品、健康志向のお菓子などが人気です。
海外では日本食品は「ヘルシー」「安全」というイメージが定着しています。越境ECでは「無添加」「オーガニック」「グルテンフリー」などの要素を前面に出すと訴求力が高まります。
最近では、日本の伝統的な発酵食品や調味料も「プロバイオティクス」として注目されており、新たな市場が生まれています。
高品質が強み!海外で売れる日本の家電製品
日本の家電製品は「高品質」「長持ち」「先進的」というイメージが世界で定着しています。
大手家電メーカーに比べ、中小企業は独自の機能やデザインに特化した製品で差別化を図ることがポイントです。
例えば、特定の美容効果に特化した美顔器や、日本の調理法に適した調理器具などが越境ECで人気を集めています。
初心者でも始められる越境EC市場トレンドの掴み方
海外市場のトレンドを把握することは、越境EC成功の鍵です。
海外市場調査と聞くと難しく感じるかもしれませんが、ここでは特別な予算や専門知識がなくても実践できるトレンド調査方法を紹介します。
無料で活用できる!トレンド分析ツールと情報源
市場トレンドを把握するために、無料で利用できるツールは数多く存在します。
Google トレンド
Google トレンドは検索キーワードの人気度を国別・地域別に確認できる便利なツールです。
自社製品に関連するキーワードの検索傾向を定期的にチェックすることで、需要の変化を把握できます。
ECモールランキング
各国のECモールのランキングページも貴重な情報源です。
Amazonや現地の大手ECサイトのカテゴリー別ランキングを定期的にチェックすれば、売れ筋商品の特徴や価格帯が見えてきます。
海外市場レポート
JETROや経済産業省が公開している海外市場レポートも活用しましょう。
これらの公的機関は定期的に各国の市場動向や消費者トレンドに関する調査結果を無料で公開しています。業界ごとの詳細なデータが入手できるため、市場選定の参考になります。
SNSで見つける海外の消費者ニーズと商品需要
SNSは海外の生の消費者ニーズを探るのに最適なツールです。
Instagram、Facebook、Pinterestなどで自社商品に関連するハッシュタグを検索すれば、現地の消費者がどのような商品に関心を持っているかが見えてきます。
特に効果的なのは、現地のインフルエンサーのアカウントをフォローする方法です。
彼らが紹介する商品や、フォロワーとのやり取りから、現地で人気の商品傾向や消費者の悩みを把握できます。
コメント欄には生の声が集まるため、ニーズ調査の宝庫と言えるでしょう。
越境EC成功事例10選
越境ECで成功を収めている日本企業の事例から学びましょう。業界の異なる10社の成功例を紹介します。
1. ユニクロ(アパレル)
シンプルで高品質な日本のライフウェアで世界展開に成功しています。
中国市場ではオムニチャネル戦略と現地SNSを活用したマーケティング、気候や体型に合わせた商品調整でアジア市場の売上を拡大。
2023年には海外売上が国内を初めて上回り、グローバル売上の55%を占めるまでに成長しました。
2. DHC(化粧品)
オリーブオイル配合のスキンケア製品で台湾・香港・タイなどで人気を獲得しました。
「Made in Japan」の信頼性と現地インフルエンサーを活用したSNSマーケティングが成功の鍵です。
サンプルサイズ商品で顧客獲得後、定期購入プログラムでリピート率を向上させています。
3. 無印良品(MUJI)(生活雑貨)
「無印」というブランディングと日本的ミニマリズムで欧米市場で評価獲得。文房具やキッチン用品などの小物は「Japanese Minimalism」として人気です。
4年間で海外店舗数を206店から443店へ倍増させ、中国市場だけでも200店舗を展開し、アジア市場での存在感を高めています。
4. 久原本家(食品)
「茅乃舎だし」で北米市場に進出し、健康志向の消費者から支持獲得しています。
化学調味料不使用の天然素材だしパックは「Authentic Japanese Umami」として話題に。
Amazonからスタートし、現地高級スーパーへも展開し、日本食材の新市場を開拓しています。
5. バルミューダ(家電)
デザイン性の高いトースターや扇風機などで欧米に進出。「技術とデザインの融合」という日本家電の強みを活かした展開で注目を集めました。
当初はEC専門で市場調査しながら段階的に拡大し、高価格帯でもデザイン性と機能性で差別化に成功しています。
6. BENTO&CO(弁当グッズ)
フランス人のThomas Bertrandが京都で設立したECショップ。日本についてのブログから始まり、500ドルの在庫からスタートしました。
現在は100カ国以上にB2BとB2Cで展開し、YouTuberとのパートナーシップで集客しています。
日本の弁当文化という独自の魅力で越境ECの成功モデルとなっています。
7. Kakimori(文具)
東京・蔵前の文具店。60種類のカバーと30種類の紙からのオーダーメイドノートブックが特徴で、SNSで海外でも人気急上昇中です。
職人技と顧客体験にこだわった製品開発とDHLとの物流提携でオンライン販売を拡大し、デジタル時代にアナログ文化の価値を世界に広げています。
8. Tokyo Otaku Mode(アニメグッズ)
2,000万いいねのFacebookページから始まり、日本のポップカルチャーを世界発信。2014年に2.7億円調達し、ECを本格的に展開しました。
ユーザーは男女均等で、アジア40%、北米・南米各20%。アニメフィギュアなどを60カ国以上に出荷し、オタク文化を肯定的に再定義した越境ECの代表例です。
9. フォーサイス(ヘアケア)
「CAREPRO」ブランドのヘアケア製品でアジア市場に進出。サロン専売品の高級感と品質をアピールし、中間〜富裕層をターゲットに展開しています。
現地インフルエンサーとのコラボで認知度を高め、トライアルセットからの定期購入プログラムで安定収益確保。現地の気候や水質に合わせた商品開発が顧客満足度を向上させています。
10. エポック社(おもちゃ)
「アクアビーズ」や「シルバニアファミリー」などの知育玩具で欧米進出しました。
日本製おもちゃの安全性と独創性をアピールし、親世代をターゲットとしたマーケティングを展開。
YouTube動画が口コミを生み、越境EC販売が拡大しました。小ロットからのテスト販売で市場反応を見極め、人気商品に絞った効率的な展開で成功しています。
まとめ
越境ECは、適切な市場選定と商品選びから始まります。
日本製品の強みを活かせるカテゴリーを選び、市場のトレンドを把握しましょう。初めは小ロットから始め、成功事例に学びながら段階的に展開することが重要です。
越境ECは決して難しくありません。あなたも海外市場への第一歩を踏み出してみましょう。
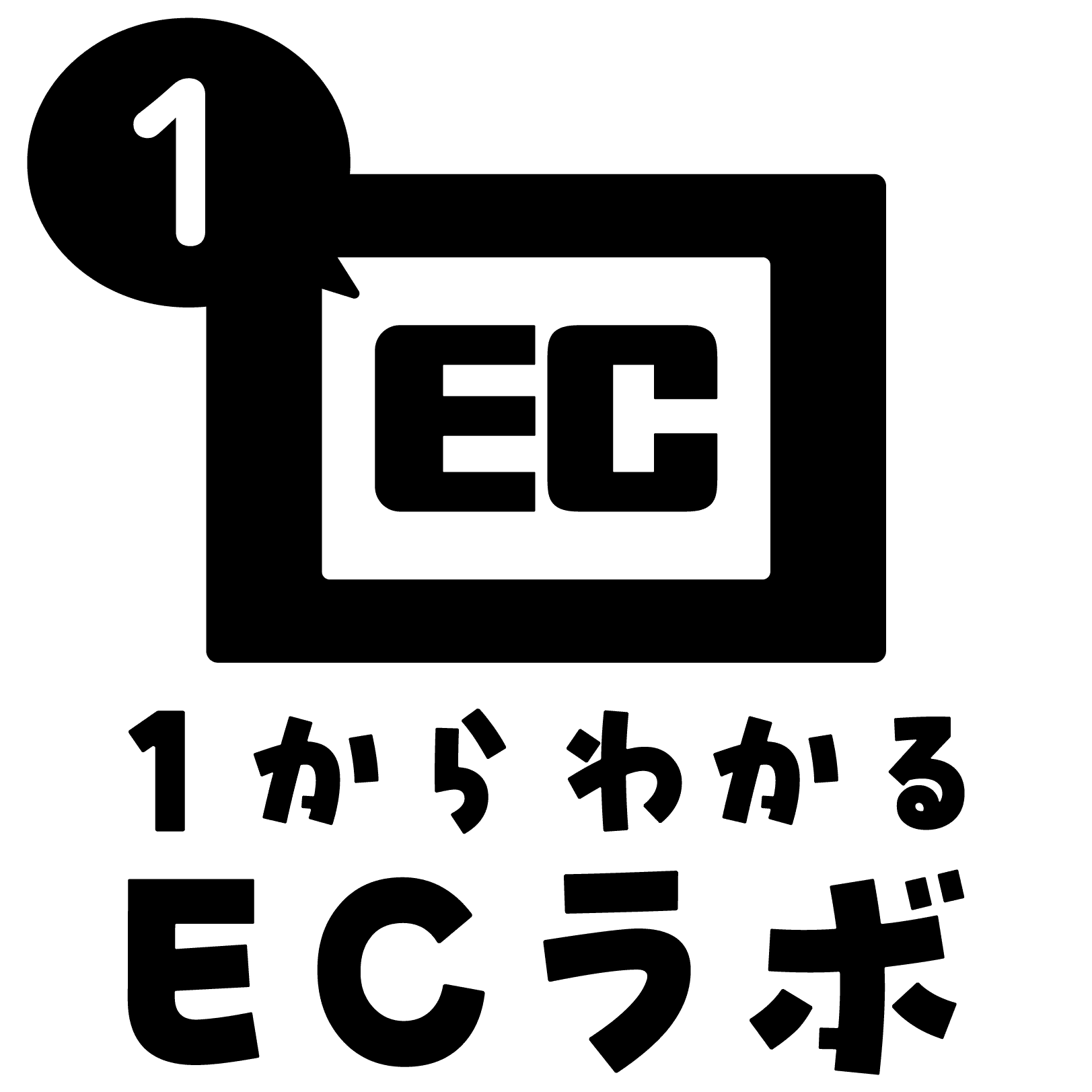






最適化-1-300x158.png)
